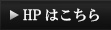賀露港を見守る古社
賀露神社
賀露神社
日本海を見下ろす小高い丘に鎮座する神社がある。賀露神社だ。創建年代は不明だが、おそらく1200年以上の歴史があるとされる。777年に吉備真備(きびのまきび)の神霊を御祭神としてお祀りしたと伝わっているし、『日本三代実録』という平安時代に編纂された歴史書に「貞観3年から元慶2年(861~78年)に神階を与えられた」との記録も見える。それほどの古社だけに、さまざまな逸話に彩られている。古くは御祭神の一柱であり、遣唐使として2度、唐に渡ったことで知られる吉備真備の逸話。真備は唐からの帰国の折に風波の難に遭い、賀露沖の宮島に漂着。約30m離れた大島にピョンと飛んで避難した。それで大島は「取り上がり島」と呼ばれ、後に「鳥ヶ島」になったという。ほかにも「みこし海上行列」や「吉備真備杯囲碁大会」など“真備伝説"にまつわる行事は多い。



賀露神社より日本海を望む。この辺りは、細く曲がりくねった道が続く住宅地。古くからの漁師町の面影が漂う。
また平安時代後期の1099年に因幡の国司、平時範(たいらのときのり)が川を下って参拝しており、以来、戦国・江戸時代を通して武門の崇敬の篤い神社でもあった。藩主が船遊びをされる時には必ずお参りになったらしい。境内には藩主・池田家や徳川将軍家の家紋が施された建造物を始め、廻船商人や漁師たちが寄進した多くの石造物が並ぶ。ちょっと不思議な感じがするのは虎の狛犬だ。何でも朝鮮半島に渡った移住者により大正の終わりごろに奉納されたとか。かの地では虎は神聖な動物とされ、台座に描かれた龍の図ともども吉祥を意味するもの。寅年を迎えたのを機に、賀露神社を参拝するのも一興である。
風格のあるたたずまい。社殿の「賀露神社」の扁額(へんがく)は、徳川の15代将軍・慶喜(よしのぶ)の兄に当たる藩主、池田慶徳(よしのり)の自筆によるもの。