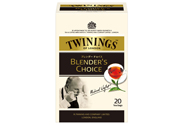三月書房
茶道、書道、華道などの道具屋が多い寺町通に、独自の品ぞろえで知られる新刊書店、三月書房がある。1950(昭和25)年に中京区寺町通二条上ル西側で宍戸恭一さんが創業した。定評のある「編集された本棚」には多彩なジャンルがボーダーレスに交錯し、文化、教育、詩歌、サブカル、心理学、アート、哲学など約1万冊の本をそろえる。店主が確かな知識と客への愛情を持ってセレクトした本がきっちり並べられている。本好きのオヤジが営む、ある意味“昭和な本屋”だ。
茶道、書道、華道などの道具屋が多い寺町通に、独自の品ぞろえで知られる新刊書店、三月書房がある。1950(昭和25)年に中京区寺町通二条上ル西側で宍戸恭一さんが創業した。定評のある「編集された本棚」には多彩なジャンルがボーダーレスに交錯し、文化、教育、詩歌、サブカル、心理学、アート、哲学など約1万冊の本をそろえる。店主が確かな知識と客への愛情を持ってセレクトした本がきっちり並べられている。本好きのオヤジが営む、ある意味“昭和な本屋”だ。
クラシックの殿堂を挙げ連ねるならば、「夜の窓」「ランブル」「築地」「柳月堂」「フランソア」……が名店だ。ジャズ喫茶ならば、「ダウンビート」「シアンクレール」「カルコ’20」「ブルーノート」「ヤマトヤ」……などなど。「ダウンビート」はつづめて「ダンビ」と通によばれ、「シアンクレール」はフランス語だろうか? いや「思案に暮れる」だろうとうわさされた。「カルコ’20」は、東海道大津の宿の次、やっと京の入り口の坂道を下る「蹴上(けあげ)」の坂道に面したジャズ喫茶で、歩道側が全面格子におさまる透明ガラス。時折、坂道を傾き走る電車が轟音(ごうおん)をとどろかせ店内を流れるジャズの上にライブでかぶさるのだった。またその“カルコのママ"というのがふるっていた。綾さんと称(よ)ばれる彼女は、長い黒髪にピタリとしたパンツにスエーター・ルック。ドキッとさせるようなスレンダー美女で、バルバラかジュリエット・グレコを髣髴(ほうふつ)させた。
クラシックやジャズ以外では「クンパルシータ」や「フレンチ・カンカン」は店名が示す通りだし、今もって名だたる「イノダコーヒ」や「六曜社」は、一向に人気が衰える気配がない。
江戸時代にはすでに京都の出版社が蝟集(いしゅう)していた寺町界隈に今もたたずむ文系書店「三月書房」は、小さいながらも恐るべき高密度なセレクションで知られるが、その購入した書籍を小脇に抱えさっそくに目を通すにふさわしい店が斜め前方の「デコイ」だ。軽い読書や店内に取りそろえられた新聞各紙の活字に視線を走らせ、手際よいマスターの珈琲さばきを愉たのしめる。四条小橋は西木屋町。専用階段をトトンと上がると暗い色調の木質で統一された小さな店内に窓からの外光がやわらかく差し込む。ガラス窓からうかがえる柳の枝と眼下をせせらぐ高瀬川。
クラシックやジャズ以外では「クンパルシータ」や「フレンチ・カンカン」は店名が示す通りだし、今もって名だたる「イノダコーヒ」や「六曜社」は、一向に人気が衰える気配がない。
江戸時代にはすでに京都の出版社が蝟集(いしゅう)していた寺町界隈に今もたたずむ文系書店「三月書房」は、小さいながらも恐るべき高密度なセレクションで知られるが、その購入した書籍を小脇に抱えさっそくに目を通すにふさわしい店が斜め前方の「デコイ」だ。軽い読書や店内に取りそろえられた新聞各紙の活字に視線を走らせ、手際よいマスターの珈琲さばきを愉たのしめる。四条小橋は西木屋町。専用階段をトトンと上がると暗い色調の木質で統一された小さな店内に窓からの外光がやわらかく差し込む。ガラス窓からうかがえる柳の枝と眼下をせせらぐ高瀬川。