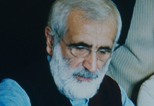(上)近年、人気を集める長崎和牛。生産者の渡部英二さん(JA長崎せいひ)が目指すのは、赤身が旨い和牛だ。「肉本来の味がする赤身にこそ、和牛の旨みが詰まっていると考えています」と常に牛の健康を考え、そのためには労力を惜しまない。
(下)南北アンデス山系原産のトマトは、17世紀末にオランダから長崎に鑑賞用として伝えられたとされる。旬のおいしさをジュースにして「おおむら夢ファーム シュシュ」で販売中。
(下)南北アンデス山系原産のトマトは、17世紀末にオランダから長崎に鑑賞用として伝えられたとされる。旬のおいしさをジュースにして「おおむら夢ファーム シュシュ」で販売中。
また歴史的に見て、長崎県は明治維新までは幕府直轄地と佐賀、島原などの諸藩に分かれていたため、一つの藩が歴史を紡いできた他県と違い、地域ごとに異なる多種多様な文化が育まれてきた。五島列島を始めとする離島も多く、島の数は971と全国一。中国や韓国などに近いことから、当然、古くから大陸との交流が盛んに行われてきた。長崎の“和華蘭文化"は、そこに端を発するもので、食文化で言えば和・洋・中が合わさった卓袱(しっぽく)料理が代表例と言える。離島のほか、多くの岬と湾、入江から形成される長崎県は、約4200㎞に及ぶ海岸線があり、北海道に次いで全国2位の長さがある海洋県。その広い海域で、アジやサバ、イサキ、タチウオ、トラフグ、ヒラメ、イセエビ、アワビなど、多くの魚介類がとれるため、水産加工品も非常に豊富。