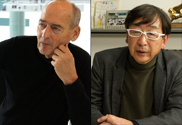本展の野外展示場に原寸大で再現されている「光の教会」(1989年/大阪府茨木市)。厳しい条件の下で生まれた小規模でシンプルな造形の礼拝堂には、美しい光の十字架がシンボリックに差し込む。撮影/松岡満男
まず紹介されるのは、安藤氏が自身の原点としている「住宅」。彼を世界的に有名にした初期の代表作である「住吉の長屋」から、圧倒的なスケールを見せる近年の作品まで、100を超える住宅建築のハイライトが並ぶ。自然との共生を重視した幾何学的な造形の打ち放しコンクリートという、安藤氏のスタイルの原型が見られる展示となっている。
この安藤氏のスタイルは、その後の教会建築でより顕著に現れる。本展では、その中でも野外展示場に原寸大で再現された「光の教会」が最大の見どころだろう。敷地的にも経済的にも厳しい条件であったが、装飾的な要素を可能な限り削ぎ落としたシンプルな造形が生まれ、美しい十字架の光が差し込む礼拝堂を実現した。インスタレーションは、十字架にガラスをはめず、安藤氏が本来計画していたかたちで再現した空間を実際に体感することができる。
一方で、「表参道ヒルズ」や「東急東横線 渋谷駅」などの都市建築において安藤氏が一貫して目指してきたのは、人が集まるための余白を生かした空間。近年の作品では中国・上海の「上海保利大劇院」なども展示されている。また周辺環境と一体化させるというのも常に彼が考えてきたこと。30年余りかけて7件もの建築を手掛けた「直島の一連のプロジェクト」のインスタレーションを見れば、それがよく分かるだろう。どのようなプロジェクトでも「場所を読む」ことからスタートして「その場所にしかできない建築」を目指す安藤氏。直島では長い年月を経て風景のように周辺環境と一体化した建築を見ることができる。
この安藤氏のスタイルは、その後の教会建築でより顕著に現れる。本展では、その中でも野外展示場に原寸大で再現された「光の教会」が最大の見どころだろう。敷地的にも経済的にも厳しい条件であったが、装飾的な要素を可能な限り削ぎ落としたシンプルな造形が生まれ、美しい十字架の光が差し込む礼拝堂を実現した。インスタレーションは、十字架にガラスをはめず、安藤氏が本来計画していたかたちで再現した空間を実際に体感することができる。
一方で、「表参道ヒルズ」や「東急東横線 渋谷駅」などの都市建築において安藤氏が一貫して目指してきたのは、人が集まるための余白を生かした空間。近年の作品では中国・上海の「上海保利大劇院」なども展示されている。また周辺環境と一体化させるというのも常に彼が考えてきたこと。30年余りかけて7件もの建築を手掛けた「直島の一連のプロジェクト」のインスタレーションを見れば、それがよく分かるだろう。どのようなプロジェクトでも「場所を読む」ことからスタートして「その場所にしかできない建築」を目指す安藤氏。直島では長い年月を経て風景のように周辺環境と一体化した建築を見ることができる。

「上海保利大劇院」(2014年/中華人民共和国・上海)は、オペラハウスを含む文化コンプレックス。人が集う余白のある空間を目指し、ソリッドとボイド、キューブとチューブが交錯した空間を生み出した。撮影/小川重雄