
防府天満宮御誕辰祭(毎年8月3日~5日)では、最終日に花火大会が開催される。天満宮から打ち上げられる、色とりどりの花火が防府の夏を彩る。この防府天満宮御誕辰祭は、学問の神様である菅原道真公のご生誕を祝う祭りで、夜には万灯の夕べが行われ、1000余のろうそくで参道が照らされる。
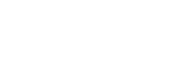
幕末の熱き志士たちが駆け抜けた・防府
激動の幕末、維新の舞台となる
幕末、長州藩の志士たちが維新に向けて、活躍したことはご存じの通りだ。長州藩の萩城下出身の吉田松陰は、実家の敷地内に松下村塾を作り、久坂玄瑞、高杉晋作、伊藤博文、山縣有朋、吉田稔麿、入江九一、前原一誠、品川弥二郎、山田顕義などの面々を教育したことでも有名だ。こうした長州藩の志士たちが薩摩や長崎、そして京都や江戸などに出向く際に、必ず通った場所がある。瀬戸内に面し、藩の南に位置する三田尻である。
ここに上陸すれば、幕末に藩主が居た山口に最も近い距離にあり、各所に戦艦を受け入れる港を持つ重要な土地であった。この瀬戸内海上、交通の地理的、地形的有用性から、多くの船や人が出入りし、とりわけ1867(慶応3)年の薩摩との倒幕に向けての出兵準備、調整、出港に際しては、三田尻の持つ港湾や、その周辺の機能が最大限に活用されたのだ。三田尻港から程近い、三田尻御茶屋や防府天満宮周辺にも、こうした熱き志士たちの足跡が残されている。もちろん、三田尻界隈には、西郷隆盛、坂本龍馬、大久保利通、中岡慎太郎、島津久光といった他藩の幕末に活躍した志士らも三田尻港から長州に上陸した。
ここに上陸すれば、幕末に藩主が居た山口に最も近い距離にあり、各所に戦艦を受け入れる港を持つ重要な土地であった。この瀬戸内海上、交通の地理的、地形的有用性から、多くの船や人が出入りし、とりわけ1867(慶応3)年の薩摩との倒幕に向けての出兵準備、調整、出港に際しては、三田尻の持つ港湾や、その周辺の機能が最大限に活用されたのだ。三田尻港から程近い、三田尻御茶屋や防府天満宮周辺にも、こうした熱き志士たちの足跡が残されている。もちろん、三田尻界隈には、西郷隆盛、坂本龍馬、大久保利通、中岡慎太郎、島津久光といった他藩の幕末に活躍した志士らも三田尻港から長州に上陸した。





