
作家 和田竜(わだ・りょう)
1969(昭和44)年大阪府生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。2003(平成15)年、映画脚本『忍ぶの城』で城戸賞を受賞。2007年、同作を小説化した『のぼうの城』でデビュー。同作は直木賞候補となり、映画化され、2012年公開。2014年、『村上海賊の娘』で吉川英治文学新人賞および本屋大賞を受賞。他の著作に『忍びの国』『小太郎の左腕』がある。ちなみに名前の「竜(りょう)」は坂本龍馬から取ったもの。
1969(昭和44)年大阪府生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。2003(平成15)年、映画脚本『忍ぶの城』で城戸賞を受賞。2007年、同作を小説化した『のぼうの城』でデビュー。同作は直木賞候補となり、映画化され、2012年公開。2014年、『村上海賊の娘』で吉川英治文学新人賞および本屋大賞を受賞。他の著作に『忍びの国』『小太郎の左腕』がある。ちなみに名前の「竜(りょう)」は坂本龍馬から取ったもの。
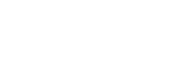
村上海賊が時を超えてよみがえる
Photo TONY TANIUCHI Text Junko Chiba
和田竜氏の『村上海賊の娘』を読まずして、瀬戸内を旅する醍醐味を味わうことはできない。「織田水軍VS 村上水軍」の第一次木津川合戦を描いたこの歴史巨編は、戦国時代の瀬戸内の海賊たちの荒々しくも人間味にあふれる魅力を浮き上がらせ、その壮大な歴史の織りなすロマンが旅心を盛り上げてくれるのだ。いざ、文庫本4冊をかばんに詰めて瀬戸内へ。村上海賊と“ 旅の一戦” を交えようではないか。
「夏の芸予諸島を本州側の高台から俯瞰(ふかん)すると、その奇観に息を吞(の)むほどである。島というより巨大な山といった方がふさわしい濃緑の巨塊があちこちで突き出し、かなたの四国本土にまで連なっている。その山々を淡青(たんせい)の海が浸す様は、異界を思わせる美しさだ」―和田氏は、毛利方の乃美宗勝(のみむねかつ)と児玉就英(こだまなりひで)が能島(のしま)に向かい船を漕(こ)ぎ出す場面で、芸予諸島の景観をこんなふうに表現している。これはそのまま、取材旅行で因島(いんのしま)の高台から瀬戸内の島々を一望した時に氏の目に映じたものだ。
「こんなにきれいな所だったんだと改めて驚きました。と同時に、そういう美しい場所に海賊がいたというギャップに物語性を感じました。またそれだけ美しいからこそ、実際に船で通ろうとすると難しい。一つの島に山々が重なり、その島々が幾十にも重なり、しかも潮流が速く複雑で、船の行く手を阻むかのよう。でも、地元の人にはわかるんですよ。村上海賊が昔、金を取って水先案内をしていたことが実感できました」 と話す和田氏だが、瀬戸内の島々との出合いはこの時が初めてではない。まずは『村上海賊の娘』につながる氏の原体験をたどる。
「当時はまだ瀬戸内しまなみ海道がなかったので、船で回ったようです。僕はあまり記憶がないのですが、父から『ここに海賊が住んでいたんだぞ』と教わり、子ども心に『かっこいいな』と思ったことを強烈に覚えています。その時に買ってもらった村上家の家紋入りの赤いふんどしを家の階段の壁に貼って、朝夕通るたびに眺めていたし、東京に引っ越してからも家族で昔話になると『因島に村上海賊が……』みたいな話になったし、村上海賊はかっこいい存在として心に植え付けられたんですね。イメージ的には西洋のパイレーツで、何となく悪くて、でも勇ましくてという認識でした」
それは将来を見通した天の計らいだったのか。
和田氏は4作目に初めて週刊連載の依頼を受けて小説を書くことになった時、すぐに「そうだ、村上海賊を書こう」と思い立ったそうだ。
ただ史料を読み込み、現地取材を進める中で、海賊に対するイメージは変わった。「瀬戸内の海賊を研究されている松山大学の山内譲教授が盛んに言っておられるように、日本の海賊はパイレーツとは違う。そういう要素もあるけど、水先案内や船の護衛、海の通航料徴収、交易など、さまざまな働きをしていました。だから『海賊=パイレーツ』と訳すのは短絡的。『海賊』という言葉は世界に通じる日本語となるのがふさわしいと思いますね」と和田氏は言う。
「こんなにきれいな所だったんだと改めて驚きました。と同時に、そういう美しい場所に海賊がいたというギャップに物語性を感じました。またそれだけ美しいからこそ、実際に船で通ろうとすると難しい。一つの島に山々が重なり、その島々が幾十にも重なり、しかも潮流が速く複雑で、船の行く手を阻むかのよう。でも、地元の人にはわかるんですよ。村上海賊が昔、金を取って水先案内をしていたことが実感できました」 と話す和田氏だが、瀬戸内の島々との出合いはこの時が初めてではない。まずは『村上海賊の娘』につながる氏の原体験をたどる。
海賊ってかっこいい!
大阪に生まれた和田氏は、生後3カ月から中学2年までを広島で過ごした。小学生の頃には家族旅行で中国地方の名所・旧跡を回り、因島や大三島(おおみしま)なども訪れたという。「当時はまだ瀬戸内しまなみ海道がなかったので、船で回ったようです。僕はあまり記憶がないのですが、父から『ここに海賊が住んでいたんだぞ』と教わり、子ども心に『かっこいいな』と思ったことを強烈に覚えています。その時に買ってもらった村上家の家紋入りの赤いふんどしを家の階段の壁に貼って、朝夕通るたびに眺めていたし、東京に引っ越してからも家族で昔話になると『因島に村上海賊が……』みたいな話になったし、村上海賊はかっこいい存在として心に植え付けられたんですね。イメージ的には西洋のパイレーツで、何となく悪くて、でも勇ましくてという認識でした」
それは将来を見通した天の計らいだったのか。
和田氏は4作目に初めて週刊連載の依頼を受けて小説を書くことになった時、すぐに「そうだ、村上海賊を書こう」と思い立ったそうだ。
ただ史料を読み込み、現地取材を進める中で、海賊に対するイメージは変わった。「瀬戸内の海賊を研究されている松山大学の山内譲教授が盛んに言っておられるように、日本の海賊はパイレーツとは違う。そういう要素もあるけど、水先案内や船の護衛、海の通航料徴収、交易など、さまざまな働きをしていました。だから『海賊=パイレーツ』と訳すのは短絡的。『海賊』という言葉は世界に通じる日本語となるのがふさわしいと思いますね」と和田氏は言う。





