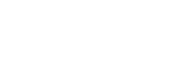
江戸時代の風情が残る岩国・柳井
錦帯橋を中心にした城下町・岩国
日本を代表する木組みのアーチ橋として有名な錦帯橋。1674(延宝2)年に完成した錦帯橋は、1950(昭和25)年の台風による洪水で流失するまでの276年間もの間、不落の橋として、ここ岩国に往時の姿のまま在り続けた。その構造や耐久性から“奇跡の橋"ともいわれ、この優美な姿は歌川広重や葛飾北斎、司馬江漢といった有名絵師によって描かれている。
錦帯橋は、岩国藩(現・山口県岩国市)の三代目の藩主、吉川広嘉(きっかわひろよし)によって、城と城下町をつなぐために掛けられたものである。そもそも岩国の領主となった吉川家は、代々長州藩毛利家の家臣として仕えた。関ヶ原戦いで西軍(豊臣方)として毛利輝元とともに戦った初代藩主の吉川広家は、毛利家の存続のために徳川家康に尽力したという。そして、江戸時代を通じてここ岩国藩(3万石)を吉川家が治めることとなる。岩国の初代藩主となった広家は、すぐに築城と町の整備を始める。城は、戦後の緊張感から防御に重きを置き、横山の山頂に築き、蛇行した錦川を天然の外堀として、両岸を中心に城下町を造営。そのため、政治と暮らしを分断する、流れが速い200mという広い川幅の錦川には、橋が必要となったわけだ。
錦帯橋は、岩国藩(現・山口県岩国市)の三代目の藩主、吉川広嘉(きっかわひろよし)によって、城と城下町をつなぐために掛けられたものである。そもそも岩国の領主となった吉川家は、代々長州藩毛利家の家臣として仕えた。関ヶ原戦いで西軍(豊臣方)として毛利輝元とともに戦った初代藩主の吉川広家は、毛利家の存続のために徳川家康に尽力したという。そして、江戸時代を通じてここ岩国藩(3万石)を吉川家が治めることとなる。岩国の初代藩主となった広家は、すぐに築城と町の整備を始める。城は、戦後の緊張感から防御に重きを置き、横山の山頂に築き、蛇行した錦川を天然の外堀として、両岸を中心に城下町を造営。そのため、政治と暮らしを分断する、流れが速い200mという広い川幅の錦川には、橋が必要となったわけだ。

1674(延宝2)年に完成した同じ錦帯橋は、その美しさは江戸時代中期ごろから評判になっており、参勤交代の大名たちは山陽道から外れていた岩国に立ち寄り、橋をめでてから江戸に向かったという。向かいの山、横山の頂きには、1608(慶長13)年に初代藩主吉川広家が築いた岩国城がそびえる。





