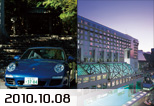瞑想の道
山の寺寺院群では、16の寺々をつなぐように整備された「瞑想の道」を散策しながら、若き等伯の足跡をたどるのが楽しい。その展望所から七尾市街を望む。
山の寺寺院群では、16の寺々をつなぐように整備された「瞑想の道」を散策しながら、若き等伯の足跡をたどるのが楽しい。その展望所から七尾市街を望む。
空白の18年間
等伯は養父母が相次いで亡くなったのを機に、33歳で上洛したといわれている。しかし、その時から大徳寺三門に天井画と柱絵を描いて脚光を浴びる51歳までの18年間は、実は記録がほとんど残っていない。七尾時代にすでに一流の絵師であったのに、こんなに長い間、世に出ることがなかったとは、不思議と言えば不思議である。小説『等伯』は、その空白期間を埋めるように、等伯の行動を生き生きと描き出す。特に信長が比叡山を焼き打ちした年に決行した「上洛時の物語」がおもしろい。あらましはこうだ。
「等伯が畠山家の政争に巻き込まれたせいで、養父母が自害。七尾から逃げるようにして、等伯は京都を目指す。ところが、近江で浅井と織田の戦いが激化し、琵琶湖に出る道は封鎖されていた。やむなく妻子を敦賀に残し、等伯は単身、“修験者ルート"を取ったが、そこでまた秀吉勢、明智勢、織田勢の戦火に見舞われる。しかも、一人で織田勢を蹴散らした等伯は“お尋ね者"になってしまう。そのために何とか本法寺にたどり着いたものの、入れてもらえず……」
というふうに、等伯は心静かに仏と対峙する絵師とは対極の、まるで忍者のごとき活劇を演じる。内に秘めた激しさを噴出させるように。そんな等伯を支えたのは、「田舎の絵仏師で終わりたくない」という絵に対する情熱であり、絵師として都で独り立ちすることを応援してくれる家族への愛情だったのだ。
旅の締めくくりに翌日の早朝、千里浜方面に向かった。「あの辺りの海岸では、強風になぎ倒されそうになりながらも果敢に立つ松が多く見られますよ」という情報をキャッチして。行ってみて納得。「『松林図屏風』に描かれた世界が、確かにここにはある」と実感した。
七尾に生まれた等伯がたどり着いた画境――遠ざかるにつれて次第に薄くなり、やがてもやの中に消えていくあの「松林図屏風」の絵さながらの光景に、等伯の生き方が二重写しになるようだった。
「等伯が畠山家の政争に巻き込まれたせいで、養父母が自害。七尾から逃げるようにして、等伯は京都を目指す。ところが、近江で浅井と織田の戦いが激化し、琵琶湖に出る道は封鎖されていた。やむなく妻子を敦賀に残し、等伯は単身、“修験者ルート"を取ったが、そこでまた秀吉勢、明智勢、織田勢の戦火に見舞われる。しかも、一人で織田勢を蹴散らした等伯は“お尋ね者"になってしまう。そのために何とか本法寺にたどり着いたものの、入れてもらえず……」
というふうに、等伯は心静かに仏と対峙する絵師とは対極の、まるで忍者のごとき活劇を演じる。内に秘めた激しさを噴出させるように。そんな等伯を支えたのは、「田舎の絵仏師で終わりたくない」という絵に対する情熱であり、絵師として都で独り立ちすることを応援してくれる家族への愛情だったのだ。
旅の締めくくりに翌日の早朝、千里浜方面に向かった。「あの辺りの海岸では、強風になぎ倒されそうになりながらも果敢に立つ松が多く見られますよ」という情報をキャッチして。行ってみて納得。「『松林図屏風』に描かれた世界が、確かにここにはある」と実感した。
七尾に生まれた等伯がたどり着いた画境――遠ざかるにつれて次第に薄くなり、やがてもやの中に消えていくあの「松林図屏風」の絵さながらの光景に、等伯の生き方が二重写しになるようだった。


山の寺寺院群
(上)日蓮宗京都本法寺末・本延寺。等伯の生家・奥村家の菩提寺だ。等伯が26歳の時に彩色寄進した「日蓮聖人坐像」を本道奥の位牌堂に祀る。天井画は等伯の子孫に当たる日本画家の仲春洋氏によるもの。
(下)曹洞宗総持寺直末・龍門寺。ある時期に4代七尾城主・義元の菩提寺である興徳寺を合併吸収したので、畠山氏の文書や家臣の墓碑などが多く残る。等伯筆の「達磨図」を所蔵。
(上)日蓮宗京都本法寺末・本延寺。等伯の生家・奥村家の菩提寺だ。等伯が26歳の時に彩色寄進した「日蓮聖人坐像」を本道奥の位牌堂に祀る。天井画は等伯の子孫に当たる日本画家の仲春洋氏によるもの。
(下)曹洞宗総持寺直末・龍門寺。ある時期に4代七尾城主・義元の菩提寺である興徳寺を合併吸収したので、畠山氏の文書や家臣の墓碑などが多く残る。等伯筆の「達磨図」を所蔵。