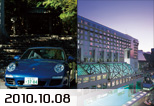金栄山 妙成寺
日蓮宗の本山・妙成寺。日蓮聖人の孫弟子・日像聖人を開祖とする。本堂、祖師堂、五重塔など、桃山建築10棟の重要文化財は、1581年より能登国を治めた前田家の寄進による。
日蓮宗の本山・妙成寺。日蓮聖人の孫弟子・日像聖人を開祖とする。本堂、祖師堂、五重塔など、桃山建築10棟の重要文化財は、1581年より能登国を治めた前田家の寄進による。
中でも注目したいのは本延寺。等伯の生家・奥村家の菩提寺でもあるこの寺には、等伯が26歳の時に彩色寄進した「日蓮聖人坐像」が祀られている。残念ながら、等伯による彩色が認められるのは、右袖の一部のみ。法衣の青や袈裟の朱などの鮮やかな色は、後世に塗り替えられたものらしい。それでも等伯が仏画だけではなく、木像の彩色にも関わっていたことが分かる点で興味深い。染色業で養われた色彩感覚が生きており、それが上洛して、後の等伯の色鮮やかな作品にも発揮されたように思う。
本延寺はまた、安部龍太郎の小説『等伯』で重要な役割を担っている。上洛の際、京都の本法寺を頼るよう紹介状を持たせてくれたのが、本延寺の日便和尚という設定なのだ。実際、本法寺は本延寺の本山であり、京都に出た当初、等伯は本法寺を拠点に活動している。史実に近い交わりが描かれているように感じる。
また、養家・長谷川家の菩提寺である長壽寺や、28歳の等伯が開眼供養に合わせて描いたと伝わる「日蓮聖人画像」を所蔵する實相寺、上洛して以降に広く各派の様式を学んだことが見てとれる「達磨図」を所蔵する龍門寺など、興味は尽きない。自身も熱心な法華信者であった等伯の足跡を求めて「瞑想の道」をたどる寺巡りに、心が洗われるようだ。
寺ではあと一つ、羽咋市にある妙成寺も訪ねておきたいポイントだ。田んぼの広がる道を進むと、五重塔が忽然と現れる。栩葺きの屋根は五重塔としては全国唯一だという。ここには等伯筆の「日乗上人像」「仏涅槃図」と、等伯筆と伝わる「日蓮聖人像」が現存し、等伯との深い関わりを示唆する。また、ここは京都の本圀寺派の寺。等伯が仏画を納めたこの寺をつてに、20代の頃からすでに京都を往来し、当時の先端の技法も学んでいたことが推察される。
本延寺はまた、安部龍太郎の小説『等伯』で重要な役割を担っている。上洛の際、京都の本法寺を頼るよう紹介状を持たせてくれたのが、本延寺の日便和尚という設定なのだ。実際、本法寺は本延寺の本山であり、京都に出た当初、等伯は本法寺を拠点に活動している。史実に近い交わりが描かれているように感じる。
また、養家・長谷川家の菩提寺である長壽寺や、28歳の等伯が開眼供養に合わせて描いたと伝わる「日蓮聖人画像」を所蔵する實相寺、上洛して以降に広く各派の様式を学んだことが見てとれる「達磨図」を所蔵する龍門寺など、興味は尽きない。自身も熱心な法華信者であった等伯の足跡を求めて「瞑想の道」をたどる寺巡りに、心が洗われるようだ。
寺ではあと一つ、羽咋市にある妙成寺も訪ねておきたいポイントだ。田んぼの広がる道を進むと、五重塔が忽然と現れる。栩葺きの屋根は五重塔としては全国唯一だという。ここには等伯筆の「日乗上人像」「仏涅槃図」と、等伯筆と伝わる「日蓮聖人像」が現存し、等伯との深い関わりを示唆する。また、ここは京都の本圀寺派の寺。等伯が仏画を納めたこの寺をつてに、20代の頃からすでに京都を往来し、当時の先端の技法も学んでいたことが推察される。