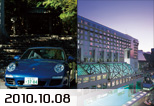七尾の一本杉通り
(左)一本杉通りの鳥居醤油店。藩政時代から代々、大森屋の屋号で和菓子屋を営んでいたが、1911年に鳥居花鳥堂になり、さらに25年に醤油製造業に商売替えした。
(右)七尾市の一本杉通りは、城下町風情が漂うところ。土蔵造りによる七尾町家の典型的な形を今に伝える高澤ろうそく店は、1892年の創業。信仰にあつい地元北陸を始め、全国に和ろうそくを納めている。
(左)一本杉通りの鳥居醤油店。藩政時代から代々、大森屋の屋号で和菓子屋を営んでいたが、1911年に鳥居花鳥堂になり、さらに25年に醤油製造業に商売替えした。
(右)七尾市の一本杉通りは、城下町風情が漂うところ。土蔵造りによる七尾町家の典型的な形を今に伝える高澤ろうそく店は、1892年の創業。信仰にあつい地元北陸を始め、全国に和ろうそくを納めている。
絵仏師・等伯の足跡
城から七尾市街に下り、一本杉通りを訪ねた。ここは、七尾駅前を流れる御祓川に架かる紅い欄干の仙対橋から、御祓公民館まで450m続くまっすぐの通りだ。600年以上の歴史があるそうで、「畠山時代にはもう城山麓から所口湊や府中屋敷にかけて一里にわたって連なる町並みがあった」とも言われる。
おそらく等伯の養家の染物屋も、この辺りで商いをしていたはず。そんな想像をしながら通りを歩くのもまた一興だ。
さて、次の目的地は山の寺寺院群。桜川を挟んで、前田利家が築いた居城(現・小丸山公園)の対岸にある舌状台地に16の寺院が点在する。利家が1581年に織田信長より能登一国を与えられた折に、奥能登方面からの陣地に転用する目的で、真言寺院を除く各宗派寺院29カ寺を配置したのが始まりだ。つまり「前田家ゆかりの寺々」だが、寺自体はそれ以前より開かれており、絵仏師であった等伯との関係も深い。
等伯は養父の長谷川宗清を師匠とし、着物に直接絵を描く染物業の仕事をしつつ、仏画の技術を磨く修業に打ち込んでいた。早くから絵の才を認められ、今も能登を中心に富山、新潟などの寺院に多くの作品が残っている。
おそらく等伯の養家の染物屋も、この辺りで商いをしていたはず。そんな想像をしながら通りを歩くのもまた一興だ。
さて、次の目的地は山の寺寺院群。桜川を挟んで、前田利家が築いた居城(現・小丸山公園)の対岸にある舌状台地に16の寺院が点在する。利家が1581年に織田信長より能登一国を与えられた折に、奥能登方面からの陣地に転用する目的で、真言寺院を除く各宗派寺院29カ寺を配置したのが始まりだ。つまり「前田家ゆかりの寺々」だが、寺自体はそれ以前より開かれており、絵仏師であった等伯との関係も深い。
等伯は養父の長谷川宗清を師匠とし、着物に直接絵を描く染物業の仕事をしつつ、仏画の技術を磨く修業に打ち込んでいた。早くから絵の才を認められ、今も能登を中心に富山、新潟などの寺院に多くの作品が残っている。