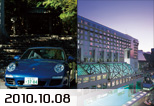七尾城跡
等伯の時代、能登国を統治していたのは能登畠山家。七尾湾を見下ろす天険の地に、七つの尾根にまたがる山城、七尾城を築いた。本丸のほか多くの屋敷群を備えた「山上都市」である。
等伯の時代、能登国を統治していたのは能登畠山家。七尾湾を見下ろす天険の地に、七つの尾根にまたがる山城、七尾城を築いた。本丸のほか多くの屋敷群を備えた「山上都市」である。
七尾に吹く文化の風
菊尾・亀尾・松尾・虎尾・梅尾・竹尾・龍尾の名を持つ七つの尾根にまたがるこの巨大な山城は、険しい山岳部を巧みに利用した「難攻不落の城」として知られていた。
かつての威風堂々とした姿の片鱗を、今も残る石垣に見る思いだ。その石垣に沿うように上っていくと、まっすぐ伸びた杉木立がすがすがしさを醸す空間に出る。軍馬を調教した桜馬場である。さらに城道を行き本丸に出ると、市街と能登島の浮かぶ海を一望する、胸のすくような景色が広がる。まさに“お山の大将"気分だ。
「聞きしに及び候より名地、(加)賀・越(中)・能(登)の金きん目もくの地形と云い、要害山海に相応し、海うみ頬づら嶋しま々じまの躰ていまでも、絵え 像ぞうに写し難き景勝までに候」―七尾城を落とした上杉謙信は、初めてここに登城した際の感想を、こう書状にしたためている。
また特徴的なのは、単なる「立てこもりの砦」ではなく、日常的な政治活動や生活の拠点城郭であったこと。多くの屋敷が集結して城下町を形成した。とりわけ等伯が生まれた頃の七尾は、7代義総の下で全盛期を迎えていた。義総自身が古典研究に熱心な文化人であったし、畠山家はもともと室町幕府の政務を総括する管領の地位にもあった“大物"でもあるので、都から多くの文化人が訪れたという。邸ではたびたび和歌や連歌の会が催されたとも伝わる。
そうして七尾は京の文化との交流を重ねながら、地域に根差した独自の能登畠山文化を開花させた。等伯は、その文化の風を受けて育ったと言っていいだろう。
かつての威風堂々とした姿の片鱗を、今も残る石垣に見る思いだ。その石垣に沿うように上っていくと、まっすぐ伸びた杉木立がすがすがしさを醸す空間に出る。軍馬を調教した桜馬場である。さらに城道を行き本丸に出ると、市街と能登島の浮かぶ海を一望する、胸のすくような景色が広がる。まさに“お山の大将"気分だ。
「聞きしに及び候より名地、(加)賀・越(中)・能(登)の金きん目もくの地形と云い、要害山海に相応し、海うみ頬づら嶋しま々じまの躰ていまでも、絵え 像ぞうに写し難き景勝までに候」―七尾城を落とした上杉謙信は、初めてここに登城した際の感想を、こう書状にしたためている。
また特徴的なのは、単なる「立てこもりの砦」ではなく、日常的な政治活動や生活の拠点城郭であったこと。多くの屋敷が集結して城下町を形成した。とりわけ等伯が生まれた頃の七尾は、7代義総の下で全盛期を迎えていた。義総自身が古典研究に熱心な文化人であったし、畠山家はもともと室町幕府の政務を総括する管領の地位にもあった“大物"でもあるので、都から多くの文化人が訪れたという。邸ではたびたび和歌や連歌の会が催されたとも伝わる。
そうして七尾は京の文化との交流を重ねながら、地域に根差した独自の能登畠山文化を開花させた。等伯は、その文化の風を受けて育ったと言っていいだろう。

七尾城本丸跡。桜馬場に向かう階段や野面積みの石垣に、約600年前の勇壮な姿を彷彿とする。城周辺に広がる城下町は経済的にも繁栄し、能登畠山文化が開花した。