
蓮華会(れんげえ)で頭役(とうやく)が奉納する弁才天像の一つ。1566( 永禄9)年には戦国大名・浅井久政( 長政の父)が頭人(とうにん)を務め、小谷(おだに)城で祀られた弁才天を奉納したという。
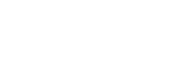
辯才天
写真・トニータニウチ 文・千葉潤子
神仏習合のパイオニア
船を降り、港から島を見上げる。急峻な斜面の中腹に立つ朱色の三重塔に向かって、長く急な石段が駆け上がっている。165段。「きついというほどでもないが、楽でもない」微妙な段数だ。巡礼者や参拝者が祈りを捧げながら上ったことから、「祈りの階段」の名が付けられたという。程なく宝厳寺の本堂に着いた。入母屋(いりもや)造り、檜皮葺(ひわだぶ)き。寺内最大の建物だ。「弁才天堂」とも呼ばれるここに、秘仏の本尊・弁才天像が祀られている。「日本三弁才天」の中でも最も古いことから「大」の字を付けて「大弁才天」と称される。内陣正面の須弥壇(しゅみだん)の厨子(ずし)に安置され、60年に一度の開帳なので、めったにこの秘仏を見ることはできない。が、須弥壇の周りは眷属(けんぞく)の十五童子と多くの弁才天像が祀られていて、圧倒される思いだ。
弁才天像は、宝厳寺最大の祭礼「蓮華会(れんげえ)」で、人々の代表として選ばれた頭人(とうにん)によって奉納された新造のもの。1000年以上続く祭礼だけにその数は膨大で、内陣裏にも年ごとに新造されてきた多くの像が安置されているそうだ。宝厳寺の弁才天信仰の歴史を物語っている。もっとも現在は、新造は頭人にとって大変な負担になるため、宝厳寺から預かった弁才天像で渡御することもある。それでも頭人を務めることは昔も今も最高の栄誉だ。行事が終わると、「蓮華の長者」「蓮華の家」としてその名が留められるという
弁才天像は、宝厳寺最大の祭礼「蓮華会(れんげえ)」で、人々の代表として選ばれた頭人(とうにん)によって奉納された新造のもの。1000年以上続く祭礼だけにその数は膨大で、内陣裏にも年ごとに新造されてきた多くの像が安置されているそうだ。宝厳寺の弁才天信仰の歴史を物語っている。もっとも現在は、新造は頭人にとって大変な負担になるため、宝厳寺から預かった弁才天像で渡御することもある。それでも頭人を務めることは昔も今も最高の栄誉だ。行事が終わると、「蓮華の長者」「蓮華の家」としてその名が留められるという





