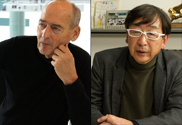安藤忠雄(あんどう・だだお)
建築家。独学で建築を学び、1969年に安藤忠雄建築研究所を設立。代表作に「光の教会」、「ピューリッツァー美術館」、「表参道ヒルズ」。79年に「住吉の長屋」で日本建築学会賞を受賞し、以降、日本芸術院賞、プリツカー賞、文化功労者、国際建築家連合(UIA) ゴールドメダルなど受賞多数。97年より東京大学教授、03年より同大学名誉教授。2004年より「美しいまち・大阪」の実現に向けて、大川・中之島一帯を中心に桜を植樹する「桜の会・平成の通り抜け」の活動に呼びかけ人として参加。2016年東京オリンピック招致のためのグランドデザインの監督を務める。
建築家。独学で建築を学び、1969年に安藤忠雄建築研究所を設立。代表作に「光の教会」、「ピューリッツァー美術館」、「表参道ヒルズ」。79年に「住吉の長屋」で日本建築学会賞を受賞し、以降、日本芸術院賞、プリツカー賞、文化功労者、国際建築家連合(UIA) ゴールドメダルなど受賞多数。97年より東京大学教授、03年より同大学名誉教授。2004年より「美しいまち・大阪」の実現に向けて、大川・中之島一帯を中心に桜を植樹する「桜の会・平成の通り抜け」の活動に呼びかけ人として参加。2016年東京オリンピック招致のためのグランドデザインの監督を務める。

建築家 安藤忠雄
建築が可能にする“もっと元気になる日本の街づくりとは? ”
建築が可能にする“もっと元気になる日本の街づくりとは? ”
Photo Masahiro Goda(1ページ目)、Text Junko Chiba
「街は人間が生活を楽しむ場所」だとする安藤忠雄氏。
自然に親しみ、文化を感じながら歩くのが楽しい。
そんな街づくりから、日本人の疲弊した心と体に“元気のエキス”を注入しようとしている。
自然に親しみ、文化を感じながら歩くのが楽しい。
そんな街づくりから、日本人の疲弊した心と体に“元気のエキス”を注入しようとしている。
都市の活力が人を元気にする
「近頃、日本人は非常にくたびれていますね。好奇心が薄れて、家に閉じこもる人が増えたように見えます。その原因の一端は街づくりにあるのではないか。経済的効率だけを考えて建築物を乱立させる、そんなふうにしてつくられた都市に、日本人が絶望しているのではないか。日本人がかつての元気を取り戻すためには、歩くのが楽しい、活力あふれる都市づくりを目指さなくてはいけない。私はそう考えています」
建築家としての安藤忠雄氏の原点は、フランスで活躍した近代建築の巨匠、ル・コルビュジエが手がけた「ロンシャンの礼拝堂」にある。「建築とは何か」を模索し続けていた若き日に、多くの人々が集うこの教会の写真を見た時、氏はその答えを見出したのだという。
「建築とは、人々が集まり、対話する場を創造する行為である」――。
以来、「訪れる人々が希望の光を感じ、互いの対話を促進できるような建築物を、街をつくりたい」という情熱に衝き動かされるように仕事を続けてきた安藤氏。街に、人々が生活を楽しむ場としての魅力を創出したい思いでいっぱいだ。
「たとえばパリやニューヨークは、ぶらぶら歩いていて楽しいでしょ?1850年代に、都市を文化的な生活が楽しめる場所にするという明確な目標の下に進められた計画の賜物です。公園などの人工的な自然と、オペラハウスや美術館、博物館などの文化施設、さらにはカフェやショップ、画廊等が絶妙に配置され、今なお人々の心を魅了しています。都市はこういうふうにつくらなけ
ればいけない。私はもう30年以上前から、『都市の記憶を継承しながら、歩いて楽しい街をつくる』姿勢を貫き、さまざまな都市に対して提案を続けています」