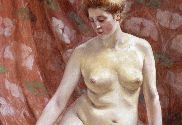正統派にして大衆的
暁斎は1831(天保2)年生まれ。7歳の時に浮世絵師歌川国芳に入門し、彼が生涯真摯(しんし)に取り組むことになる「写生」との重要な出会いを果たす。そして10歳の時に、改めて駿河台狩野派の絵師に弟子入りした。当時の狩野派は、幕府の仕事を一手に引き受けつつ全国にピラミッド型の組織を確立している巨大絵師集団で、駿河台狩野派はその中でもかなり高く格付けされる一派。暁斎はこうしたいわゆる「狩野派らしい狩野派」を誇る環境で修業を重ね、19歳で皆伝の印として号(画家としての名)を与えられた。
しかし修業を終えた後の暁斎は、狩野派の画家として寺院の障壁画作製などに参加しつつも、浮世絵や戯画、本の挿絵といった町絵師としての活動にも積極的に携わっていく。彼はもともと、決められた画題を決められた画法で描く狩野派の絵師として生涯を終えるつもりはなかったのだろう。また、狩野派に学んだ絵師としては珍しく、暁斎は浮世絵や南画、京都の四条円山派など狩野派以外の画派の技術と表現を詳細に学び、写生にも情熱を傾けて、画力を高めるためのあらゆる試みに手を出した。そのかいあってか、程なくして町人からの注文が殺到するようになり、自身の画譜を出版するほどの流行絵師となった。
ちなみに明治維新後、狩野派は幕府という後ろ盾をなくして活躍の場を失う。特に明治初期は官民ともに西洋化一辺倒で、日本の伝統文化が顧みられなかった時代。狩野派の絵師の多くは、この時期に転廃業を余儀なくされた。日本美術が再評価され始めるのは、明治10年代半ば以降。政府が内国勧業博覧会などを開催するようになってからである。
明治維新の年、暁斎は38歳。日本画不遇の時期を人気町絵師として生き抜いた暁斎は、狩野派に学んだ人間としては特異な存在だった。
しかし修業を終えた後の暁斎は、狩野派の画家として寺院の障壁画作製などに参加しつつも、浮世絵や戯画、本の挿絵といった町絵師としての活動にも積極的に携わっていく。彼はもともと、決められた画題を決められた画法で描く狩野派の絵師として生涯を終えるつもりはなかったのだろう。また、狩野派に学んだ絵師としては珍しく、暁斎は浮世絵や南画、京都の四条円山派など狩野派以外の画派の技術と表現を詳細に学び、写生にも情熱を傾けて、画力を高めるためのあらゆる試みに手を出した。そのかいあってか、程なくして町人からの注文が殺到するようになり、自身の画譜を出版するほどの流行絵師となった。
ちなみに明治維新後、狩野派は幕府という後ろ盾をなくして活躍の場を失う。特に明治初期は官民ともに西洋化一辺倒で、日本の伝統文化が顧みられなかった時代。狩野派の絵師の多くは、この時期に転廃業を余儀なくされた。日本美術が再評価され始めるのは、明治10年代半ば以降。政府が内国勧業博覧会などを開催するようになってからである。
明治維新の年、暁斎は38歳。日本画不遇の時期を人気町絵師として生き抜いた暁斎は、狩野派に学んだ人間としては特異な存在だった。


(右)河鍋暁斎《閻魔と地獄太夫図》 明治前半 河鍋暁斎記念美術館蔵
地獄太夫は地獄柄の着物姿の室町時代の遊女。一休和尚を感服させたと伝わる。太夫が地獄を訪れ、生前の罪を映すという浄玻璃鏡(じょうはりのかがみ)の前に立つ姿と閻魔を描く。閻魔の興味津々ぶり、太夫の堂々とした表情の対比が面白い。
(左)河鍋暁斎《暁斎楽画第九号 地獄太夫 がいこつの遊戯ヲゆめに見る図》
1874(明治7)年 河鍋暁斎記念美術館蔵 ※前期のみ展示
地獄太夫は、暁斎が多く描いたモチーフの一つ。眠る太夫と骸骨たちの競演。夢の中の骸骨たちは琴、尺八、三味線、囲碁、相撲とあらゆる遊興にふける。楽しげな様子、動きの豊かさ、そしてデッサンの破綻(はたん)のなさに驚かされる。
地獄太夫は地獄柄の着物姿の室町時代の遊女。一休和尚を感服させたと伝わる。太夫が地獄を訪れ、生前の罪を映すという浄玻璃鏡(じょうはりのかがみ)の前に立つ姿と閻魔を描く。閻魔の興味津々ぶり、太夫の堂々とした表情の対比が面白い。
(左)河鍋暁斎《暁斎楽画第九号 地獄太夫 がいこつの遊戯ヲゆめに見る図》
1874(明治7)年 河鍋暁斎記念美術館蔵 ※前期のみ展示
地獄太夫は、暁斎が多く描いたモチーフの一つ。眠る太夫と骸骨たちの競演。夢の中の骸骨たちは琴、尺八、三味線、囲碁、相撲とあらゆる遊興にふける。楽しげな様子、動きの豊かさ、そしてデッサンの破綻(はたん)のなさに驚かされる。