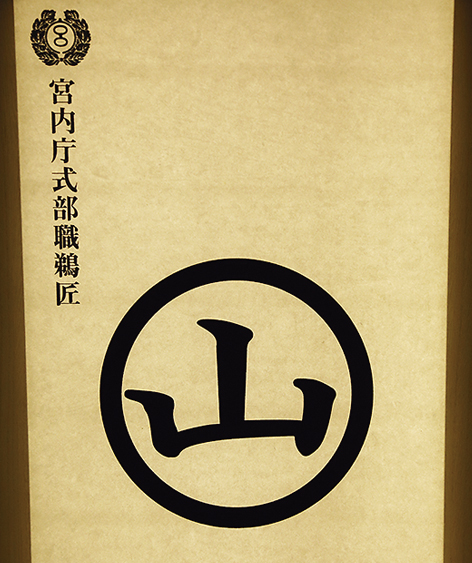
夜の帳とばりが降りるころ、舟首に篝かがり火びを焚き、十羽を超える鵜を手縄で操る鵜う匠しょうが登場すると、見物客は大いに沸き立つ。かつてはただの漁だったが、今では古典漁法を披露する、観光事業にもなっている。ある意味では伝統芸能にも通じる漁だ。
古くは王族から始まり、戦国武将たちが好んだように、鷹狩は時の実力者たちの、権威の象徴ではあったが、〈食〉とは結び付かず、ただの殺生とも言える。
時に鵜飼も残酷な行いだと言われることもあるが、鵜匠と鷹匠の立場を分けたのは〈食〉の有る無しだったのではなかろうか。
それにしても巧うまい方法を考えたものである。日本のみならず、中国やヨーロッパでも行われていたという鵜飼。鵜は噛か まずに丸呑みして、喉のどで溜た めるから、鮎に傷が付かない。故に鮮度が保てるので遠方まで運ぶことができる。献上品として珍重された所ゆ以えんである。
源頼朝は長良川で出会った鮎鮨の旨うまさに感嘆し、鵜飼を見物した織田信長は鵜匠を雇い入れる。同じく鵜飼を目の当たりにした徳川家康は、鮎の石焼きに舌鼓を打ち、その後鵜匠たちに多額の金子を払い、江戸城まで鮎を献上させた。
多くの武将たちが鮎に魅了されたのは、ただその味わいだけではないように思える。
古くは王族から始まり、戦国武将たちが好んだように、鷹狩は時の実力者たちの、権威の象徴ではあったが、〈食〉とは結び付かず、ただの殺生とも言える。
時に鵜飼も残酷な行いだと言われることもあるが、鵜匠と鷹匠の立場を分けたのは〈食〉の有る無しだったのではなかろうか。
それにしても巧うまい方法を考えたものである。日本のみならず、中国やヨーロッパでも行われていたという鵜飼。鵜は噛か まずに丸呑みして、喉のどで溜た めるから、鮎に傷が付かない。故に鮮度が保てるので遠方まで運ぶことができる。献上品として珍重された所ゆ以えんである。
源頼朝は長良川で出会った鮎鮨の旨うまさに感嘆し、鵜飼を見物した織田信長は鵜匠を雇い入れる。同じく鵜飼を目の当たりにした徳川家康は、鮎の石焼きに舌鼓を打ち、その後鵜匠たちに多額の金子を払い、江戸城まで鮎を献上させた。
多くの武将たちが鮎に魅了されたのは、ただその味わいだけではないように思える。
