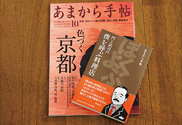(左)大阪天満宮。度々の火災に遭い、他の天満宮のようなきらびやかさはないが、大阪の献身的な氏子に支えられた歴史を持つ。
(右)大阪天満宮の表門(大門)から本殿。表門の天井を見上げると、方角盤がある。東西南北と十二支の名を令書で、それぞれの動物が彫刻されている。酉の位置に鳳凰が配される。
(右)大阪天満宮の表門(大門)から本殿。表門の天井を見上げると、方角盤がある。東西南北と十二支の名を令書で、それぞれの動物が彫刻されている。酉の位置に鳳凰が配される。
アーケード付きの商店街にはおよそ600の店があり、老舗の専門店や雑貨店、飲食店など、大阪あきんどの集大成のような幅広い店が並ぶ。天井の赤い鳥居が、天神さんゆかりの風情を感じさせる。地域の人々にとって、天神さんは今も無くてはならない存在なのだ。その天神さんから、〝天四〞辺りでJR天満駅方面へと歩き、天満駅前北本通りを進むと、天満市場のビルが現れる。
天満市場は、かつて青物市場と呼ばれ、江戸時代には現在の北区天満から天神橋、南天満公園付近一帯に広がる天下の台所・大坂を象徴する市場だった。大川に面して水運の便が良かったことから発展し、一時は毎日、数万人の商人が集まっていたという。野菜を売った農家や商人が天神さんを詣で、歓楽街で遊び、界隈は大いににぎわいを見せた。だが、1931(昭和6)年に天満市場は大阪市中央卸売市場に統合。現在の天満市場は、再建されたものだ。
天満市場は、かつて青物市場と呼ばれ、江戸時代には現在の北区天満から天神橋、南天満公園付近一帯に広がる天下の台所・大坂を象徴する市場だった。大川に面して水運の便が良かったことから発展し、一時は毎日、数万人の商人が集まっていたという。野菜を売った農家や商人が天神さんを詣で、歓楽街で遊び、界隈は大いににぎわいを見せた。だが、1931(昭和6)年に天満市場は大阪市中央卸売市場に統合。現在の天満市場は、再建されたものだ。