
アフリカや中南米など、遠く海外からやって来て、製材の時を待つ丸太たち。関家具には約20億円分の木材がストックされているという。
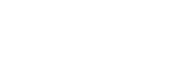
一枚板のテーブルで
勝負
勝負
Photo Masahiro Goda Text Junko Chiba
関家具の年輪
有明佐賀空港から大川へ。筑後川を渡りこの町に入ると、多くの家具店の看板が目に飛び込んでくる。言わずもがなの「家具の町」である。さらに関家具を目指して国道208号線を南へ走り、幡保交差点辺りに来た時、ちょっと驚いた。「大川家具街道」と呼ばれるその周辺は“関家具だらけ"。カラフルなペガサスビルの「大川デザインショールーム」を始め、8棟のショールームや店舗が軒を連ねている。興味はまず、町の成り立ちへと引き付けられていく。
古くから大川は、筑後川上流の大分県・日田の森で伐採される木材が川を下って運ばれてくる集積地として栄えた所。その中心が大川家具発祥の地とされる榎津である。
時は室町後期の1536年、足利12代・義晴の家臣の弟であった榎津久米之介が、この地の船大工の技術を生かして作らせた指し物が家具生産の始まりだと伝えられる。
時代が下がって江戸後期には、田ノ上嘉作という建具職人が、釘を使わず、木に穴や切り込みを入れて組み立てる「榎津指物」を開発。以後、田ノ上一門の名工たちが、時代に合った新しい技術を習得し、今日の大川家具の礎を築いたという。
古くから大川は、筑後川上流の大分県・日田の森で伐採される木材が川を下って運ばれてくる集積地として栄えた所。その中心が大川家具発祥の地とされる榎津である。
時は室町後期の1536年、足利12代・義晴の家臣の弟であった榎津久米之介が、この地の船大工の技術を生かして作らせた指し物が家具生産の始まりだと伝えられる。
時代が下がって江戸後期には、田ノ上嘉作という建具職人が、釘を使わず、木に穴や切り込みを入れて組み立てる「榎津指物」を開発。以後、田ノ上一門の名工たちが、時代に合った新しい技術を習得し、今日の大川家具の礎を築いたという。





