
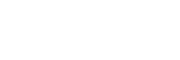
高まる⁉ 日本株の相対的優位性
田嶋智太郎 経済アナリスト
円安がもたらす日本の上場企業の株価への影響
3月下旬、ついに1ドル=125円台まで円安が進む場面を垣間見ることとなった。急激な円安進行の直接的原因は、日銀による「指し値オペ(公開市場操作)」の連続実施である。国債を決まった利回りで無制限に買い入れる措置が1日に複数回発動されたのは初のことで、さすがに市場もかなり敏感に反応した。
日銀が金利を人為的に低く抑え込む政策に執着する一方で、米連邦準備制度理事会(FRB)は3月に利上げ実施の決定を下し、今後も早期の追加利上げ余地を講じていく可能性が高いとされる。結果、市場では日米金利差が今後も拡大し続けるとの思惑が強まり、円安・ドル高に拍車がかかることとなった。その後、一段の円安進行を牽制するような動きが財務省や官邸あたりに見られたことで、いったんは121円台まで値を戻す動きも見られた(執筆時)が、なおも趨勢(すうせい)的な円安傾向が続くとの見方に変わりはない。
折からの供給制約に伴う国際的なモノの需給の引き締まりに、ウクライナ侵攻に伴う対ロシア制裁が拍車をかける格好で、資源・エネルギー、穀物の価格をはじめあらゆるモノの物価が上昇傾向をたどっているなか、多くのモノを輸入に頼る日本社会にとって円安の進行が痛手であることに間違いはない。
円安によって日本の輸入金額が膨らみ、結果的に財政赤字が拡大することも一層の円売り材料と受け止められる。円安を「リスク」とする側面から捉えれば、まさに悪循環である。
とはいえ、円安が進むとそれだけ少なからぬ輸出企業の収益にとってプラスの面があることも事実である。また、海外の投資家や旅行者などにとって、円安の進行は日本への関心を高める要因の一つとなる。訪日外国人観光客がもたらすインバウンド需要が、コロナショック以前の状態を取り戻すまでには今少しの時間を要することとなろうが、日本の資産への投資を外国人が検討する際には、円安・自国通貨高が一つの魅力となり得る。
日銀が金利を人為的に低く抑え込む政策に執着する一方で、米連邦準備制度理事会(FRB)は3月に利上げ実施の決定を下し、今後も早期の追加利上げ余地を講じていく可能性が高いとされる。結果、市場では日米金利差が今後も拡大し続けるとの思惑が強まり、円安・ドル高に拍車がかかることとなった。その後、一段の円安進行を牽制するような動きが財務省や官邸あたりに見られたことで、いったんは121円台まで値を戻す動きも見られた(執筆時)が、なおも趨勢(すうせい)的な円安傾向が続くとの見方に変わりはない。
折からの供給制約に伴う国際的なモノの需給の引き締まりに、ウクライナ侵攻に伴う対ロシア制裁が拍車をかける格好で、資源・エネルギー、穀物の価格をはじめあらゆるモノの物価が上昇傾向をたどっているなか、多くのモノを輸入に頼る日本社会にとって円安の進行が痛手であることに間違いはない。
円安によって日本の輸入金額が膨らみ、結果的に財政赤字が拡大することも一層の円売り材料と受け止められる。円安を「リスク」とする側面から捉えれば、まさに悪循環である。
とはいえ、円安が進むとそれだけ少なからぬ輸出企業の収益にとってプラスの面があることも事実である。また、海外の投資家や旅行者などにとって、円安の進行は日本への関心を高める要因の一つとなる。訪日外国人観光客がもたらすインバウンド需要が、コロナショック以前の状態を取り戻すまでには今少しの時間を要することとなろうが、日本の資産への投資を外国人が検討する際には、円安・自国通貨高が一つの魅力となり得る。
