目指せ100万頭 その黄金時代
政府が再び牧羊事業に目を向けたのは、大正に入ってから。第一次大戦が勃発し、敵国となった豪州から羊毛の輸入ができなくなったのだ。慌てた政府は大正6年、「第二次めん羊増殖計画」を樹立。100万頭の増殖を目指して全国に5箇所の種羊場を設け、各種奨励施策を推進した。「北海道にはこの時、札幌・羊ヶ丘展望台で有名な月寒と滝川に、2つの種羊場が設立されました。そして昭和に入って軍需が増大し、太平洋戦争が終結した20年には、全国の飼養頭数が10年前の約4倍に当たる18万頭に達しました。うち北海道は4万8000頭。3万1000戸の数万人が飼養経験を持つに至り、戦後の黄金期の礎が築かれたように思います。すでに大正年間に不況の煽りで本州にあった3つの種羊場は閉鎖され、残った北海道の2つの種羊場が日本の羊産業の中心的な役割を担っていたんですね」
戦争が終われば、もう羊毛を国に納める必要はない。農家はまず、自家産の羊毛で毛糸を紡ぎ、靴下や手袋、セーターなどをつくった。やがて紡績工場の復旧にともない、羊毛の委託加工の事業が勃興した。
羊飼いたちは町の人が羨む純毛製品を手に入れたのだ。これはいい、衣料品不足が補えると、農家はめん羊の飼養頭数を増やし、郊外の一般の家庭でもめん羊を飼うようになった。「仔羊はひっぱりだこの人気だった」という。
こうして羊飼養熱が高まり、飼育頭数は鰻上り。昭和32年には、94万5000頭のピークを迎えたのである。
政府が再び牧羊事業に目を向けたのは、大正に入ってから。第一次大戦が勃発し、敵国となった豪州から羊毛の輸入ができなくなったのだ。慌てた政府は大正6年、「第二次めん羊増殖計画」を樹立。100万頭の増殖を目指して全国に5箇所の種羊場を設け、各種奨励施策を推進した。「北海道にはこの時、札幌・羊ヶ丘展望台で有名な月寒と滝川に、2つの種羊場が設立されました。そして昭和に入って軍需が増大し、太平洋戦争が終結した20年には、全国の飼養頭数が10年前の約4倍に当たる18万頭に達しました。うち北海道は4万8000頭。3万1000戸の数万人が飼養経験を持つに至り、戦後の黄金期の礎が築かれたように思います。すでに大正年間に不況の煽りで本州にあった3つの種羊場は閉鎖され、残った北海道の2つの種羊場が日本の羊産業の中心的な役割を担っていたんですね」
戦争が終われば、もう羊毛を国に納める必要はない。農家はまず、自家産の羊毛で毛糸を紡ぎ、靴下や手袋、セーターなどをつくった。やがて紡績工場の復旧にともない、羊毛の委託加工の事業が勃興した。
羊飼いたちは町の人が羨む純毛製品を手に入れたのだ。これはいい、衣料品不足が補えると、農家はめん羊の飼養頭数を増やし、郊外の一般の家庭でもめん羊を飼うようになった。「仔羊はひっぱりだこの人気だった」という。
こうして羊飼養熱が高まり、飼育頭数は鰻上り。昭和32年には、94万5000頭のピークを迎えたのである。
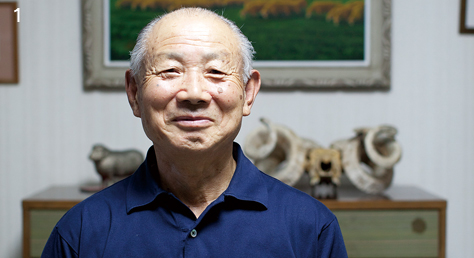

1 北海道めん羊協議会の顧問を務める近藤知彦さん。
道立種羊場に就職して以来、めん羊の改良、生産物の利用と
調査研究に携わってきた。
2 「エドウィン・ダン記念館」にある、
明治9年に開設した「札幌牧羊場」の写真。
ここでは、ダンの指導でメリノー種の飼育に成功した。
道立種羊場に就職して以来、めん羊の改良、生産物の利用と
調査研究に携わってきた。
2 「エドウィン・ダン記念館」にある、
明治9年に開設した「札幌牧羊場」の写真。
ここでは、ダンの指導でメリノー種の飼育に成功した。





