
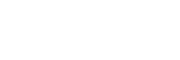
個人海外投資に必要な国際税務の基礎知識 第7回
永峰 潤 公認会計士・税理士
国際相続に関係する二つの法律
はじめに
火葬場の空高く棚引く煙。それを見ながら笠智衆が印象的なせりふを語る。日本人の死生観を極めて映画的に表現した小津作品の有名なワンシーンだ。そうしてこの瞬間から相続手続が始まる(※1)。
相続とは
今さらながら相続とは何をいうのだろうか。わが国でもかつては家の主としての戸主の地位を承継する家督相続として相続が位置付けられていたが、今日の日本において相続は私有財産制のもとで死者(被相続人という)の財産を誰かに帰属させるための制度となっている(※2)。
では相続を自分で処理するのが難しい場合、誰に相談すればいいのか。弁護士? 税理士? どちらも正しい。なぜ二つの専門家が関わるのか、その理由は相続が二つの法律と深く関わっているからである。
相続完了までの道筋
相続人間の遺産分配(遺産分割という)が相続の目的であり、分配割合を決めるに際して遺言書があるかどうかで手続は異なるが、最終的には遺産分割を実行して財産の登記・名義変更を行うことになる。ここまでは民法の守備範囲となる。それと同時か時間差で相続人ごとの相続税が計算される。これが税法の守備範囲となる。
つまり相続手続を完了するまでに民法と税法二つの法律の知識が必要となるため弁護士、税理士、二つの専門家が登場すること
になる(※3)。
国際相続特有の問題
今回はここからがテーマである。理屈っぽい話をするがしばしお付き合い願いたい。法律の一区分に、私人間の法律関係を規律する私法があり、国と私人(※4)間の法律関係を規律する公法がある。
民法は私法、税法は公法に属している。この二つの法律は目的(法益)が異なるが、相続当事者が全て日本人で財産も日本国内にとどまるならば、二つはスムーズに機能し、法律のユーザーである我々が不自由を感じたりその違いを意識することもない。
ところが、いったん、当事者として外国人が関与したり相続財産も国外所在となると、これら二つの法律の均衡関係は崩れ、お互いに亀裂が生じる可能性がある。相続人および被相続人全員が日本国籍で相続財産も全て日本国内にある、全ての要素が国内でクローズしていた場合を国内的私法関係とよび、当然ながら日本の民法が適用される。





