
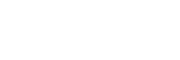
金融コラム 田嶋智太郎 経済アナリスト
米国経済の成長度合いは年後半に加速する!?
2016年の年明けは、またも中国リスクが顕在化したことなどにより、大きな波乱とともに世界の金融相場がスタートすることとなった。
昨年12月にいったん2万円の大台を回復した日経平均株価も執筆時には1万8千円割れの水準にまで値を下げており、外国為替市場でも1ドル=117円台まで円高・ドル安が進んでいる。
もちろん、これは市場心理が過度なまでに弱気に傾いたことが主因であり、主要国の経済のファンダメンタルズに大きな変化が生じたわけではない。その意味では、昨年8月、9月にも見られた一時的な不安の連鎖現象であろうと思われるが、今後も中国や中東、北朝鮮などのリスクが相場を大きく揺さぶる可能性については常に警戒を怠れないことも事実である。 もともと筆者は、2016年の相場について大まかに前半はドル/円や日本株の調整が生じやすく、調整一巡を経て後半は年末に向け大きく持ち直すと見ている。それは、やはり今後の米国経済の成長度合いと米当局(FRB=連邦準備制度理事会)が操る金融政策の行方との兼ね合いによるものと考えられるからである。
周知のとおり、米国ではすでに失業率が5%前後の水準にまで低下し、昨秋には米自動車大手3社が10年ぶりの賃上げに踏み切るなど、堅調な景気の回復ぶりが見て取れる。目下は徐々に人々の賃上げ期待が盛り上がり始めている模様であるが、その期待が広範囲に広がり、じっくりと浸透し、多くの人々の消費マインドが全体に上向くまでは少々時間もかかることであろう。よって、米国経済の成長度合いは時間が経過するごとに加速していく(=成長カーブが鋭角になっていく)ものと考えられる。
昨年12月にいったん2万円の大台を回復した日経平均株価も執筆時には1万8千円割れの水準にまで値を下げており、外国為替市場でも1ドル=117円台まで円高・ドル安が進んでいる。
もちろん、これは市場心理が過度なまでに弱気に傾いたことが主因であり、主要国の経済のファンダメンタルズに大きな変化が生じたわけではない。その意味では、昨年8月、9月にも見られた一時的な不安の連鎖現象であろうと思われるが、今後も中国や中東、北朝鮮などのリスクが相場を大きく揺さぶる可能性については常に警戒を怠れないことも事実である。 もともと筆者は、2016年の相場について大まかに前半はドル/円や日本株の調整が生じやすく、調整一巡を経て後半は年末に向け大きく持ち直すと見ている。それは、やはり今後の米国経済の成長度合いと米当局(FRB=連邦準備制度理事会)が操る金融政策の行方との兼ね合いによるものと考えられるからである。
周知のとおり、米国ではすでに失業率が5%前後の水準にまで低下し、昨秋には米自動車大手3社が10年ぶりの賃上げに踏み切るなど、堅調な景気の回復ぶりが見て取れる。目下は徐々に人々の賃上げ期待が盛り上がり始めている模様であるが、その期待が広範囲に広がり、じっくりと浸透し、多くの人々の消費マインドが全体に上向くまでは少々時間もかかることであろう。よって、米国経済の成長度合いは時間が経過するごとに加速していく(=成長カーブが鋭角になっていく)ものと考えられる。





