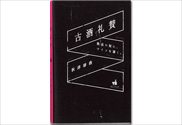日本には、その風土にあった薬酒あり
日本においても薬酒の歴史には古い。奈良正倉院に
伝わる文書の一つにも薬酒に関する記述はあり、天
平11(739)年のものとされている。さらに古くからの
薬酒として、正月に飲まれることで知られる「屠蘇(と
そ)酒」がある。屠蘇酒は中国後漢時代の華陀(かだ)
という名医によって創製され、漢方とともにわが国
に伝えられた薬酒だ。やがて漢方が日本の医学とし
て定着するにつれて、漢方書に基づく薬酒や日本の
風土に合わせた独自の薬酒が造られるようになっ
た。その代表が慶長7年(1602)に創製された「養命
酒」。生薬の特性として、2種類以上を組み合わせると
効能の幅を広げるといわれ、養命酒においてはシャ
クヤク、ジオウ、ケイヒ、トチュウなど14種類の生薬を
酒に溶け込ませ、相互に作用させている。地酒ならぬ
地薬酒として和歌山県には「忍冬酒」、愛知県には「保
命酒」などがあるというが口にされた読者はいるだ
ろうか。

日本における薬用酒の代表「養命酒」。